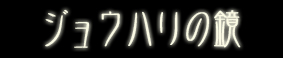 |
|
「駄目です」 きっぱりと言い放つアンリエットに、シャーロックは大きな目を瞬かせ、ネロは不満げに唇を尖らせた。一方、エルキュールはその返答を予想していたような面もちで俯き、コーデリアも軽く肩を落としている。 「でもでも、アンリエットさん!」 シャーロックは、手にした封筒をアンリエットへと突き出した。 「せっかくテレビ局から招待状がきてるんですよ〜?」 「だから駄目だと言っているんです」 アンリエットは柳眉を寄せたまま、シャーロックを見下ろした。 「それと同じ物は、私の方にも届いています」 「そうなんですか?」 少しだけ柔らかになったアンリエットの声音に、ミルキィホームズの四人は首を傾げる。アンリエットは彼女達を見渡すと、小さな溜め息を吐いた。 「オオエドテレビ局から、貴方達ミルキィホームズへの出演依頼でしょう?」 確認するかのような口調に四人は顔を見合わせ、アンリエットへと向き直ると大きく頷いた。 「だったら、どうして駄目なんですか?」 「そうだよ、僕たちがもっと有名になれるチャンスじゃん!」 汚名挽回だよ、と言葉を続けるネロに、エルキュールはネロの探偵服の裾を掴み、「それを言うなら汚名返上です……」と囁いている。 「貴方達をそのような低俗な番組に出させるわけにはいきません」 「低俗……ですか?」 きっぱりと言い放つアンリエットに、コーデリアは軽く眉を寄せた。 「怪盗と対峙する探偵を中継するというのなら分かります。ですが、たかがTV番組の為に探偵を集めて競わせるだなんて、低俗じゃなければ何だというのです?」 そして再び四人を見渡し、深い溜め息を吐いた。 「ですので、そのような番組への出演は、生徒会長として許可するわけにはいきません」 その言葉に、シャーロックは納得したような面もちで頷いた。 「アンリエットさんがそう言うなら、仕方ないです〜」 「ちょっともったいない気もするけどね」 ネロは苦笑いを浮かべているが、それでも彼女の言い分には納得したらしく、肩をすくめている。 それぞれ納得した様子のミルキィホームズを見渡し、アンリエットが眉根を緩めた。小さく息を吐くと、生徒会長室の扉が軽く叩かれる。アンリエットが「どうぞ」と促すと、コック服姿の石流が姿を見せた。 「失礼します」 挨拶すると、石流は銀色のワゴンを押して入っていく。ミルキィホームズの四人が何事かと振り返り、彼の一挙一動を見つめていたが、彼は生徒会室の中央にあるソファーとテーブルまでワゴンを運ぶと、切れ長の瞳をアンリエットへと向けた。 「こちらにセッティングしたので宜しいでしょうか」 「お願いします」 アンリエットが頷き返すと、石流はワゴンの二段目から折り畳んだテーブルクロスを取り出し、テーブルに広げた。そしてその上にティーカップと小皿を五枚載せ、並べていく。ワゴンからテーブルの中央へと移された大きめのティーポットからは、仄かに湯気が立っていた。 「あの、アンリエットさん、これは……?」 五人分用意されたティーセットにコーデリアが目を瞬かせると、アンリエットは微笑を返した。 「昨日まで、依頼の調査で大変だったでしょう? ですので特別に、お茶とお茶菓子を用意しました」 「わぁ、有り難うございます〜!」 アンリエットの気遣いに、皆が顔を綻ばす。テーブルの上座に当たる一人掛けソファーにアンリエットが腰を下ろすと、ミルキィホームズの四人はその両側に二人ずつに分かれて、ソファーに腰を下ろした。 全員が席に着くと、石流はワゴンから、チェック柄の布で覆った籠を取り出した。そしてポットの横に置くと、被せていた布を取り払う。籠の中には、石流が作ったと思われるクッキーやティグレなど、焼き菓子がずらりと並んでいた。 「わぁ、スゴいです〜!」 シャーロックは感嘆の声を挙げた。ネロはすぐさま菓子へと手を伸ばそうとしたが、行儀が悪いと思い直したのか、慌てて引っ込める。エルキュールはネロと共にそわそわとした眼差しを石流へと向けていたが、石流は、まずアンリエットのティーカップに紅茶を注いだ。それから彼女の右隣に陣取ったシャーロックのカップに注ぎ、その隣のエルキュールのカップへと注いでいく。そしてテーブルを挟んでエルキュールの正面にいるネロのカップを紅茶で満たすと、アンリエットの左隣りに座ったコーデリアのカップに紅茶を注いだ。 柔らかなアッサムの香りが漂い、シャーロックは「いただきます」と両手を合わせて、ティーカップに口を付けた。ネロは、籠の焼き菓子を手に取って口へと放り込むと、石流がソファーの隅に退かせていたテレビのリモコンを掴み、電源を入れた。そしてボタンを操作し、件のオオエドテレビへとチャンネルを合わせる。 横長の画面に、ニュースバラエティ番組が映った。ちょうど現在収録中の大探偵トーナメントを紹介しているらしく、放送日は月末といった告知をしている。 「もう、ネロったら行儀が悪いんだから……」 アンリエットに無断でテレビを付けた事に、コーデリアが顔をしかめた。しかしアンリエットは苦笑を浮かべるだけで、特に咎めない。 他の三人も番組そのものは気になるらしく、紅茶や焼き菓子を口に運びながら、TVを凝視している。 「観覧車が……きれい……」 エルキュールの感想に、シャーロックは大きく頷いた。 「もっと上の方に行ったら、赤レンガ倉庫も見えるかもしれませんね〜」 画面の中では、進行役のアイドルがマンションの一階を歩き回りながら、イベントの内容を紹介していた。広々としたフロアには壁がなく、白い柱がずらりと並んでいる。 そのうちの一つに掛かった小さな鏡を背にし、アイドルはくるりと回転すると、びしりとポーズを決めてみせた。 「こちらに直接いらしていただければ、まだまだ参加は間に合います! 我こそはと思わん探偵の皆様、ご参加お待ちしております〜!」 そう締めくくると、カメラは会場入り口の様子へと切り替わった。参加者だけでなく野次馬も含め、それなりの人数が集まっている。カメラが横に流すように参加者達を次々に映していくと、シャーロックが目を丸くした。 「あ、レナード探偵事務所の皆さんです!」 シャーロックが指さした先には、スパッツをはいた活発そうなサイドテールの少女と小柄な金髪の少女、そして桃色の着物に身を包んだ黒髪の少女が映っていた。しかしそれも一瞬で、カメラは次々に他の参加者達を映していく。 「あの……さっき、タクトさんが二人いたような……?」 首を傾げるエルキュールに、コーデリアが顔をあげた。 「そう……? 見間違いじゃない?」 見てなかったから分からないと言葉を続けると、コーデリアは持ち上げたティーカップに口をつけた。 「タクトさんが二人もいるわけないじゃないですかぁ」 シャーロックの脳天気な笑い声に、エルキュールは「そうですよね……」と小首を傾げている。 「でもこれに参加するってことは、ちょうどコッチに来てたのかなぁ」 ネロは小さく笑いながら、籠へと手を伸ばした。そしてティグレを摘み、口元へと運ぶ。 アンリエットは、以前目を通した報告書を思い浮かべた。それによるとレナード探偵事務所は、名探偵セージ・レナードの三人の娘により運営されているらしい。三姉妹は見かけも格好もバラバラで統一感がない印象を受けたが、姉妹ゆえの連携で事件を解決し、現在は従兄弟を新所長として迎えているという。 アンリエットは、とめどめ無く語られるミルキィホームズの会話に耳を傾けながら、傍らの石流を横目で伺った。 石流は、ティーポットの横に挿し湯を入れたポットを置き、アンリエットの傍らに控えている。だが、いつも通りの無表情ではあるものの、珍しくTV画面を凝視していた。 画面には、会場であるマンションが、下から見上げた構図で映っていた。番組内の説明によれば50階建てらしく、ヨコハマ超美術館からヨコハマ駅方面へ少し寄った先、探偵博会場の近くに建設されたばかりだという。 「あの……石流さん、どうかしたんですか?」 エルキュールもアンリエット同様、TVを凝視する石流に気付いたらしい。眉を八の字に寄せる彼女に、石流は「何でもない」と返した。その低い声音に、ネロはソファーに深く背を預け、石流へと顔を向けている。 「知ってる人でもいた?」 ティグレを頬張りながら見上げるネロに、石流は軽く眉をひそめた。そして右の人差し指で、己の唇の右端を無言で叩く。その所作に、ネロは自分の唇の同じ箇所を指先で拭った。そしてそこに付いたチョコを舌先で舐め取っている。 「もう……ネロったら、まだチョコが付いてるじゃない」 コーデリアはポケットからハンカチを取り出すと、隣のネロの口元を拭い始めた。 「もう、そういうのは自分でやるってば」 ネロは迷惑そうに眉を寄せてはいるものの、大人しくコーデリアに口元を拭かれている。 二人の様子に微笑を浮かべながら、アンリエットは石流へと顔を向けた。 「そういえば石流さんは、レナード探偵事務所の方達はご存じでしたよね」 その言葉に、彼は小さく頷き返した。 レナード探偵事務所のメンバーが行った奇妙な実験により、ヨコハマの探偵学院にいた石流が、遠く離れたエドガワのレナード探偵事務所まで瞬間移動させられた事がある。その時、エドガワまで彼を迎えに行ったのがミルキィホームズの四人と根津だった。だがその時はレナード三姉妹とは入れ違いになったものの、その後頻発する謎の闇化事件の調査で出会ったと、彼女達から報告を受けている。 「では、私はこれで」 石流はそう告げると、空になったワゴンを扉近くの壁へと押した。 「後で回収に参りますので、ワゴンは廊下に出して頂ければ」 扉の前でアンリエットに向けて軽く頭を下げると、静かに扉を閉める。 微かな足音と気配がゆっくりと遠ざかっていくと、アンリエットは、シャーロックから勧められた焼き菓子を口に運んだ。ゆっくりと咀嚼してから、ティーカップを唇へと運び、温かな液体で喉を潤す。アッサムの柔らかな香りと仄かな甘みが口の中へと広がったが、アンリエットは僅かに眉根を寄せた。 用がなくなれば気を利かせて退出し、頃合いを見計らって片付けに来る石流が、「終わったら呼んで下さい」ではなく「後で回収する」と告げた。それはつまり「呼んでも居ない」という事を暗にほのめかしている。 アンリエットはティーカップをソーサーに置くと、僅かに目を細めた。 ************ |